| 鞍田 炎氏(福島) 大沢健一氏(静岡) 鈴木昭裕氏(金沢) 唐木 玲氏(京都) 中西英一(東京) |
★2003年聴きまくり 未年早々、大学、社会人のアマとプロのオケをたてつづけに3つも聴くハメになった。 金沢大、また私の住む福島にゆかりのある指揮者がかかわるステージばかり。何か不思議な糸でつながっているかのような正月だった。 1月18日は金沢大学フィルハーモニー管弦楽団の第63回定演(金沢市観光会館)、翌19日は富山シティフィルハーモニー管弦楽団のトヨタコミュニティコンサート(富山市オーバード・ホール)、26日は大阪シンフォニカー交響楽団(郡山市民文化センター)。 金大フィルと大阪シンフォニカーを指揮したのは郡山市出身の本名徹次、富山シティフィルの棒は私が大学在学中3度定演を振ってもらった堤俊作だった。異なる3つのオケ、そして2人の指揮者の全く違う個性を堪能できた。 本名は現代作品と古楽演奏のスタイルに強い関心を寄せている。現代音楽演奏を中心とするアンサンブルを率い、数年前には現代音楽と古楽演奏を学ぶためロンドンに渡っている。ラトル、アルノンクール、ジンマンら古楽演奏のスタイルを積極的に取り入れる指揮者が欧米に増えているようだが、そうした流れを日本で体現しようとしているようにも思える。ブルックナーの6番(金大フィル)、チヤイコフスキーの5番(大阪シンフォニカー)でも比較的早めのテンポを設定し、フレーズの終わりにルパートをかけるロマンチックな表現は取らない。イン・テンポでメリハリがあり、音の輪郭は明瞭で、流れは弛緩しない。 推進力を維持したままフィナーレを迎える。では無味乾燥かというとそうでもない。各楽章の主題提示、展開など構造を的確に捉え的確なテクニックでオケの音を引き出す能力があるように感じた。大事な場面ではアインザッツを出すが、大きな流れを演出するだけで細かい拍子はほとんど取らない。「あれで指揮してるんだろうか」といぶかる人もいるかもしれない。そんな指揮ぶりだった。 構成感のある説得力に富んだ音楽づくりは、情感の濃厚な音楽が好きな日本人離れした、よりドライな感性に裏打ちされている。金大フィルの定演後、楽屋を訪ねたら「パッと音が決まらないといやなんだよね」と笑っていた。実家は「薄皮饅頭」で有名な江戸時代から続く老舗の菓子店だが、音楽の「甘さ」は嫌いなようだ。 ただ、金大フィルでは指揮棒を持っていなかったのに、大阪シンフォニカーでは指揮棒を持っていた。なぜだろう。 金大フィルの皆さんには「ご苦労さま、よく頑張った」と言ってあげたい。特に、充実した響きのコントラバス、表現意欲旺盛なアンサンブルを聴かせた木管群、センス抜群のトランペット、厚みのあるトロンボーン、パフォーマンスも楽しいティンパニに敬意を表したい。新鮮な感性にあふれた本名との相性も悪くなさそうだし、心に残る学生時代のステージになったのではないだろうか。 堤の音楽を生で聴くのは大学卒業以来、約20年ぶりだ。演奏会は塩田美奈子(ソプラノ)、郡愛子(メゾ・ソプラノ)、吉田浩之(テノール)ら脂の乗った4人の歌手を迎えたオペラ・ガラ形式。舞台音楽に豊富なキャリアを持つ堤の指揮ぶりは変わっていなかった。 歌手が歌いやすいテンポにもっていこうとするが、オケがついていけない場面がままあったのは残念だった。もう少しノリのよさがあればよかったのだが。しかし、バイオリンは音が美しく、管楽器もよく鳴っていた。チェロの堀田五月、ホルンの坂井禎ら同じ時期に弾いた仲間の演奏ぶりを見ることができたのはうれしかった。 偶然とはいえ、同じ月に興味深いステージを3つも楽しめて「絶対、よい年になるに違いない」と確信したのだった。(山口さんお世話になりました。よい店も紹介してくれてありがとうございます。中西、試験頑張れよ) OB 鞍田 炎 (1985年卒、チェロ) 福島市春日町 ★第63回定演を聴いて OB 大沢健一氏 (昭和50年入学 Cb) ★充実した時間だった OB 鈴木昭裕氏 (93年入学 Tb) HP ★これでいいのか!ヴァイオリン 都合でメインプログラムのブルックナーから聴く。 ヴァイオリンはいっぱいいるなぁ。数年(?)しか違わないのに、自分の現役の頃とは比べ物にならないくらい多い。それでも、OBの賛助が出演しているのが解せない。出演者不足で悩んだ者の僻みだろうか。賛助の事を知らない現役ヴァイオリン出演者がいたのも不可思議。まあ、賛助の出演は指揮者の意思かもしれないので、詮索しない。 導入部。いい感じ。音を最初に出すヴァイオリンパートの役割は果たされた。 その後、金大フィルは大きな事故に会う事もなく進んでいく。淀みなく、もったいぶることなく、さらっと、そのなかで、所々、直管金管セクションのフォルテが色を添える。 しかし、ヴァイオリンの音って二階席まで届かないなぁ。なんでだろう。もやもやしている。ざわざわしている。 二階席から眺めていると、弓の動きが納得いかない。皆さん、他人に任せている部分が多すぎやしないかい?まったく弾けていない人は居ないようなのに、音符を弾き切っている人、そして弾き切ろうとしている人も見当たらない。 オーケストラ全体から見ると、ヴァイオリンパートは清流のなかで小石がころころ転がっている感じ。流れに逆らったりすることはないけれど、流れに乗っているとも言い難いし、そもそも流れ自体に影響を与えていない。当然、トゥッティが聴こえて来ない。 さまざまな楽器の音色の華やかさだけでなく、弦楽器のトゥッティもオーケストラの大きな魅力じゃない?これでは、オーケストラを聴きに来たものにとっては魅力が半減されてしまう。さらにトゥッティの音は、演奏する側にとってもオーケストラをやる大きなモチベーションになるはずじゃないのか。せっかく音楽する場があるのに損している。 そんな意味では、少し寂しいヴァイオリンパートだった。人がたくさんいるのに、それが生きていない。 もしかして、個人で楽器をさらうのに精一杯でオーケストラまで頭が回らないのか。でもね、オーケストラって魅惑の世界を秘めていて、その魔力に取りつかれると一生抜け出せなくなるほど。そんな魅力を味わうこともなく、一度も体験することなく4年間過ごしてしまっては、もったいない。せっかく始めたオーケストラだから、この際、少し追及してみないかい? そんなに難しいことじゃないとおもう。一人一人が完璧に弾けていなきゃ、ではない。ただ、音楽のそして合奏のルールにのっとって、一人一人が個人の責任においてぎりぎりまで出来ることをする。極端に言えば、それだけ。それだけで、みんなが共存した形のトゥッティが生まれるはず。それを、半年・一年・四年間追いつづけて欲しい。そして、演奏会当日の金大フィルが聴けたらいい。プロと同じものは望まないけれど、音楽を聴かせて欲しいとおもう。たとえ、それが一部分であっても。 具体的でないので、だから?と言われそう。まずは、いろんなオーケストラを耳にして欲しい。到達目標に決まった形はないけれど、いろいろ聴いて、あらかじめ自分自身のネタ帳を増やしておく必要がある。それから基礎練習。弓を弦の上において弾きはじめる。そんなことから振り返って欲しい。 こんなことを、ブルックナーを聴きながら考えていました。説教じみていて、年寄りくさいでしょ。 最後に。人がたくさんいるのは、それだけで大きな財産。その皆さんを、皆さん自身で生かしてあげられたらいい。オーケストラの目的は音楽作りだけど、その中にもいろんな役割があるはずだから。 ところで、ブルックナーについて、ほとんど何も言及していません。正直言って、ブルックナーに深い思い入れがないので自分自身の整理が出来ません。ご勘弁を。 文責 唐木 玲 (94年入学Vn) ↑上へ |
★2年ぶりに、金大フィルを聴いた。 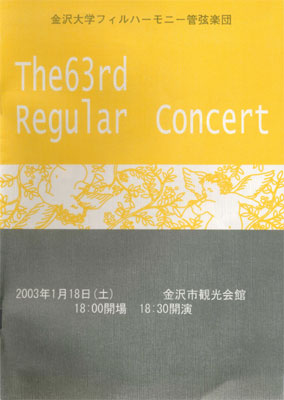 前回に聴いたのは、チャイ5だったから2年ぶりの金大フィルだ。 前回に聴いたのは、チャイ5だったから2年ぶりの金大フィルだ。日ごろHP上で好き勝手なことを書いているので、実演をちゃんと聴く必要があると思っていたところだった。ブルックナーの6番という意欲的?なプログラムに惹かれて、東京から足を伸ばした。 本当なら県立音楽堂を聴いてみたかったのだが、今回も観光会館で我慢となった。寒さも少し緩んだ18日夕刻、ホールの客入りも近年の実績からすれば、まずまずで、地味なメイン曲にも関わらず、1000人以上は確保していたように思う。2階席で、チェロのOBとともに、聴く。 今回の演奏会、まずは満足すべきものであった。 指揮者の音楽作りがかなり異色だったこと、そして、金管セクションが大健闘をしていたことは、わざわざ東京から遠出してきたことをも十分に納得させるものだった。 このコンサートでまず「目」を惹いたのは、楽器の配置が通常と大きく異なっていたこと。それも曲ごとに変えていたことだろう。 簡単に言えば、昔のトスカニーニ・NBC交響楽団やクーベリック・バイエルン放送交響楽団、ロシアのオケ等がとっていた配置だ。ヴァイオリンが両翼に配置され、バスは1stの背後に、そして、ホルンは左、直管系ラッパ(Tp、Tb,Tuba)が相対して右というのがその内容だ。最近は話題性からか、復活の兆しがある。 その効果は、成功半分疑問半分といったところ。通常、このようなことを学生は思い付き得ないから、指揮者のアイデアだろう。ファゴットとクラの位置関係も珍しいもの(下図参照)。 実はこの配置は、自分が現在所属するオケの配置と非常に近似しているため、違和感はないはずなのだが、いざ自分でそれを目の当たりにすると、驚きがある。 クラシックの世界ではカリスマ的演奏家(巨匠)が枯渇しており、何かと、新規性、奇抜性に寄りかかった演奏パフォーマンスを優先させる流行がある。音楽を必要以上に軽く構成して、一時の新鮮さを提示する反面、音楽の本当の楽しみをどこかに置き去りにする音楽家の行動に、自分は懐疑的だ。 今回の本名氏の演奏スタイルは、いま流行の古学風スタイルで、有名なところで、今をときめくラトル等の演奏スタイルと類似である。学問的な根拠や成果などは認めるべきだろうが、「音楽好き」の自分にはあまり関心がない。演奏スタイルは、作曲された瞬間から変遷を続け、ここ数十年だけでも、大編成の恣意的浪漫的スタイルの演奏と、古学派すっきり、あっさりスタイルの両極端を揺れ動いているのだと思う。 現在のスター指揮者が、軽さにしか自分の存在価値を示し得ない時代の中で、一部でもてはやされているスタイル・・、たまたま、それが金大フィルにも現れてきたということだろう。 音は短く、すっきりしていて、ビブラートも浅く、明晰なことではそれなりのもの。魔笛、未完成で、金大フィルが目標として「与えられた」その演奏スタイルに対する成果を誠実に示していたと思う。もっとも、残響の長いホールで聴けたらば、もっと、幸せだったろう。大編成のオケで、響きの豊かでないホールでのあのスタイルは、自分には十分な喜びを与えてはくれなかった。 演奏後のOBとの酒の席で、面白い話で意見が一致した。 未完成の2楽章が眠くなかった!その通りだったと思う。眠くなる前に終わっていたというのが正確だ。3拍子のマーチ?を聴いているような奇妙な感覚に襲われた。さすがに、3楽章でまた3拍子は聴きたくない(書きたくない)と思ったのは、シューベルトと同じか・・・。ロマンティックな大編成オケの演奏で育った自分には、なじめない音楽作りだ。それを学生オケに持ち込むことの見識を問うても良いのでは・・・。 尚、ホルンとファゴットの音のブレンド感は、今回のオケ配置を最大限に生かした絶妙のものだった。 しかし、ブルックナーでは、演奏者と楽器の数も増えて、指揮者の志向と音楽の特性がくい違うためか、指揮者の意図は不完全となり、金大フィル固有の地金が図らずも現れた。結果として、楽しめるものとなった。 冒頭のテンポの速さは大胆だった、続くチェロ・コンバスの豊かな表情は、これはいけるっ!と思った。6番は、ブルックナーの中でも、ちょっと捉えどころのない曲。まだ自分の中でもイメージが定着していない。しかし、1楽章のコーダ前の宇宙的な空間感覚を、そして最もブルックナーらしい2楽章を、その通りに感じさせてくれた金大フィルを称えよう。聴くたびにいつも感じるのだが、4楽章では、なぜかはちゃめちゃに暴れまくっている農民の姿を思い浮かべる。この夜は、加賀の一向一揆といったところだろう。楽しめた。 楽器配置の工夫は、ブルックーではうまく働いていた。特に金管を左右に分けたのは成功していると感じた。演奏者もそう感じているはずだ。ホルンと音が混濁しないので、トランペット奏者等にとっては非常に演奏しやすいからだ。 それにしても、直管系の金管は良かった。特にトランペットは良かった。これらのセクションで、音符の処理と演奏スタイルが統一されていて、ヨーロッパに出しても恥ずかしくないセクションだった。ブルックナーの3連符の演奏法も正しい。トランペットとトロンボーンが一列横並びではなくて、重なって並んでいるその意義を十分に示し得た演奏だ。ここ5,6年のなかで、演奏スタイルの統一と音楽が整合した、最も素晴らしい金管セクションだったと断言する。 トロンボーン・チューバも、よくコントロールされていて大人の演奏、立派の一言。久しぶりに金沢の地で、オーケストラのトロンボーン・セクションの音が聴けてうれしかった。ホルンも、彼ら彼女らなりに挑戦し、健闘していた。その心意気を認めよう。 他の楽器のことは他の人が書いてくれるだろう。 というようなわけで、指揮者の音楽作りにあまり共感しないが、それでも、満足な演奏を聴かせてくれた、金大フィルに拍手。特にブルックナーの音楽を作曲家の意図のまま違和感なく楽しませてくれた、金管セクションに大拍手を捧げたい。とりあえず、やったことがないから6番にした・・というような消極的な姿勢は、微塵も感じさせなかった。 いいコンサートだった。 文責 OB 中西英一 (東京在住 Tp) ↑上へ |