第63回定演を聴いて 昭和50年工(Cb) 大沢 健一  昭和50年入学の大沢健一です。 当時はコントラバスを弾いていました。(現在は浜松バロック協会という楽団でチェロを弾いています。)当時のコントラバスといったら、宮崎努さんでしょう。先輩にはたいへんお世話になり、影響されました。当時、金大フィルの言語世界は彼が握っていたといっても過言ではないでしょう。”ぺんぺんの服”のぺんぺんがその代表例で、「気張っている、立派、新品」などの意味で使っていたように覚えています。 さて、そんなことより先日聴いた金大フィルの演奏会についてですが、「よかった!うまい!びっくり!」でした。前回聴いたのが20年以上前ですから、当時と比べると信じられないくらいです。しいて言えば、「お行儀がよすぎる」ことが気になったくらいです。特に「未完成は?」現代の学生気質を象徴するかのように「あっさりし過ぎ」でしたね。我々では聴いていて物足りない気分でした。 しかし、魔笛序曲とブルックナー6番はよかったですね。魔笛はそのあっさり感がぴったり!我々では、きっとああは弾けません。ベートーベン風モーツアルトになってしまいます。(我々もそういえば魔笛は演奏しましたね。)ブルックナーは学生オケでここまでやれるかと思ったぐらいです。後輩の演奏ということを差し引いても、十分に感動に値する演奏会でした。(去年聴いた、チェコフィルより感動した。) 我々の時代を振り返ってみると、金大フィル成長の過渡期だと言い切れるでしょう。昭和50年は、まだ、宮守坂を登ったところに汚く暗い部室があって、練習場は坂の下、体育館の横のプレハブでした。そりゃあ「学生会館」の練習場に移ったときは感動しましたね。それから、能登へ演奏旅行に行きましたよね。小学生になんと「運命」全曲!!!を聴かせたんです。サマーコンサートの替わりだからと言って、普通の演奏会のようなプロをやるんだとかなんとかいって。 めちゃくちゃですよね。小学生が4楽章のおしまいの方であーーーあーーーって。こちらの自己満足もいいとこ。聴かされる方はたまったもんじゃありませんでした。でも、当時はそれがいいと思っていたんですね。やはり若い! (そういえば、コンバスは私ひとりでした。え!運命でコンバス1本???) 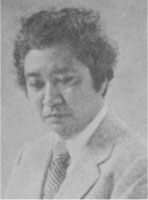 昭和51年度はなんといってもプロ指揮「伴有雄」を呼んだことが、なんといっても歴史的なことでしょう。最初の練習で「エグモント」の冒頭Fの音を弾いた事はつい昨日のことのように覚えています。最初のその1音ですら、いつもと全然違う音に聞こえました。翌年はブルックナーの初演奏(4番)。北陸初演とか。これも冒険でしたね。そして、昭和53年度は京都大学との合同演奏と「佐藤功太郎」氏をよんでのブラームス4番。卒業をまじかに控えて、最後のEの音を弾き切ったときもすごく感動しました。 今はプロ指揮も人数が多いことも、そして、トレーナーをよぶことも当然のように思われていますが、当時は貧乏な学生たちでしたからね。スキーもお金がかかるのであまり行く人がなかったくらいでしたからね。お金を出すことにはずいぶん抵抗があったんですよね。でも、お金をかけると、やはりそれだけのことが得られることもわかったんですね。いや、出した金額以上のことが学べた。それがわかっただけでもすごい進歩でした。 なんか、がむしゃらにやっていた感じですが、みんな熱かったんですね。私なんか最初の2年ぐらいはあまり真面目じゃなくて、今考えればみんなに迷惑かけたなって思う。それでもずいぶん後輩が育ってうれしかった。 そして、現在。あんなに人数が多くて、立派な演奏ができて、しっかり音楽性を追求してるなって感じがとてもすばらしいと思います。学生だからといって、妥協しないで、できるところまでみんなでがんばってもらいたいと思います。  定演終了後、鹿島屋旅館で行われた同窓会。前列左が大沢氏。 |